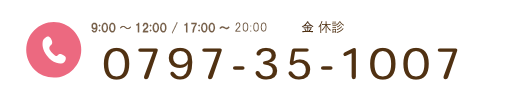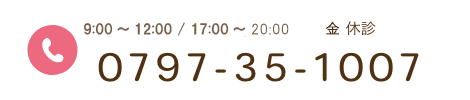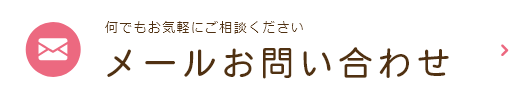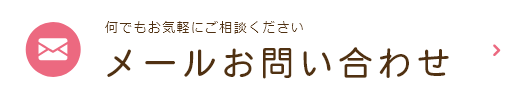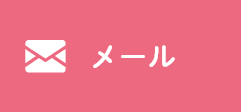12.2. FCoV排出猫の管理
繁殖猫舎や保護施設などの多頭飼育環境で、FCoV感染の有病率が高い。排出猫は糞便のFCoV RT-PCR検査によって特定でき、その 排泄期間は長く、数ヶ月、時には生涯にわたって起こることが報告されている。排出猫の検出には、毎週4回採取や、5日から28日間隔、または30日間隔で少なくとも3回検査することを述べている。 FCoVを排出している猫から非排出猫を隔離することが、感染率を下げる方法として提案されている。さらに、FCoVに感染した猫は、ストレスの多い状況にさらすべきではなく、保護施設に入ると猫のFCoV排出が増加することが知られており、これはストレスによるものと考えられている。血液のFCoV抗体検査は、抗体価と糞便中ウイルス量との間に正の相関関係があるにもかかわらず、FCoV排出猫の特定にはあまり有用ではない。抗体陽性猫64頭のうち15頭は、5~30日間隔で実施した4回の糞便PCRが陰性で、抗体陰性猫18頭のうち2頭は、PCRが陽性であった。81頭の抗体陰性猫の糞便10/81でFCoV RNAが検出された。したがって、抗体価はウィルス排出を予測できない。
12.3. FCoV排出の排除
GS-441524などの抗ウイルス薬を用いて無症状キャリア猫を治療することは、2つの理由から議論の的となっている。1つは、薬剤耐性ウイルスの発生リスクがあること、もう1つは、家庭内におけるFCoVの排除を達成・維持することが困難であることである。
薬剤耐性ウイルスの出現に関して:このような変異ウイルスは、経口投与GS-441524ではまだ実証されていない。
FCoVが遍在するため感染が容易に再導入される可能性があるため、複数の猫を飼っている家庭からFCoVを根絶することは困難であり、維持できないという懸念である。
家庭から FCoV を根絶したい飼い主には、FCoV 感染は 10 匹未満の家庭ではしばしば自然治癒することを勧める 。猫や子猫を家庭に導入する前に、優れた衛生管理、検疫、検査を行うことで達成できる場合がある。
12.4. 繁殖家における検討事項
ドイツの37の繁殖猫舎を対象に、RT-PCR法を実施した研究では、全施設で陽性だった。その後の研究では、125/222頭(56%)の猫が、月1回のRT-PCR検査を4回実施したところ3回陽性であり、持続的にウイルスを排出すると考えられた。同じ研究で、55/222頭(24%)の猫は、4回の検査すべてがFCoV RNA陰性であり、これらの猫は非排出猫であるとみなされた。
ほとんどの子猫は生後5~10週齢まで、母親由来の抗体によってFCoV感染から保護されていると考えられているため、 FIPは通常、子猫新しい家庭に移った後に発症する。妊娠した母猫を出産の2週間前に隔離し、子猫が生後5~6週齢になったら他の猫から離れた清潔な環境に移し、新しい家に行くまでそこで飼育することで、FCoVの伝播を予防できたという報告もある。一方で、子猫は生後2週齢ですでにFCoVを排出しているという報告もある。子猫に生じる社会化の問題もあり早期離乳は受け入れられていない。
12.5. シェルターなどにおける検討事項
シェルターなどの保護施設におけるFCoV感染の予防は極めて困難である。複数の猫を飼育する施設では、FCoV感染は常に存在する。入所した猫は、潜伏感染を考慮すると最低3週間は隔離する必要がある。シェルター入所後、入所時に既に感染していた猫では、ストレスにより1週間以内にFCoVの排出が劇的に増加する。ストレスによる免疫抑制効果によって、ウイルス産生の増加とFIP発症リスクにつながる可能性がある。
FCoV拡散を減らすため、熱湯によるトイレトレーの洗浄、専用のトイレトレーとスコップ、清掃用具による媒介感染を避けることに特に注意する必要がある。
理想的には、猫は1部屋あたり3頭以下で往来は制限するべきである。
FCoV感染猫に対する手術や譲渡などのストレス、FIVやFeLVとの重複感染による免疫抑制はFIP発症リスクを高める可能性がある。
12.7. FCoV陰性状態の維持
家庭でFCoV陰性状態が達成された場合、できれば新しい猫や子猫を家庭に迎える前にFCoV感染検査を実施し、それが不可能な場合はFCoV陰性になるまで隔離することにより、FCoVフリー状態を維持するべきである。