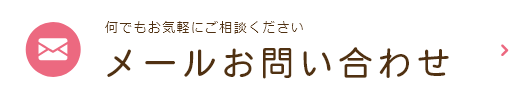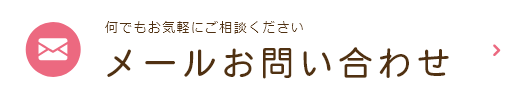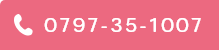尿腹症の犬43頭の予後に関する検討
Outcomes in dogs with uroabdomen: 43 cases (2006–2015) Janet A. Grimes et al. JAVMA • Vol 252 • No. 1 • January 1, 2018
尿腹症は、腎臓、尿管、膀胱、腹腔内尿道のどこかの破断によって腹腔内に尿が溜まった状態である。犬では、膀胱が最も一般的な破裂部位であり、尿道がそれに続く。腎臓と尿管からのリークは稀とされている。
犬の尿腹症は交通事故に起因することが最も多く、骨盤骨折の犬の 39% で尿路の損傷は発生するものの、そのうち尿腹症は3.6% に認められることが明らかとなった。医原性外傷は尿道カテーテルや手術で発生する可能性があり、尿管結石の手術を受けた猫の 16% で確認されている。非外傷性原因では、結石や腫瘍による尿道閉塞による過膨張、膀胱の圧迫、膀胱穿刺などがある。
診断は生化学検査で①腹水クレアチニン濃度が血清クレアチニン濃度の基準上限値の 4 倍を超える ②腹水/血清クレアチニン比が2.0以上 ③腹水/血清カリウム比が1.4以上 のうち 2 つが当てはまる場合に、感度および特異度が 100% で診断可能である。追加の検査には、遠位尿路病変に対する逆行性尿道造影または近位尿路病変に対する順行性尿路造影などの造影や試験開腹も含まれる。
尿道閉塞の治療は、尿路閉塞の場所と重症度によって異なる。症例の多くは重度の外傷を伴っており、血流量減少性ショックや高カリウム血症を発症するリスクが高くなる。術前に積極的な静脈内輸液、尿の除去、および高カリウム血症の治療が必要になる。尿路感染症を併発している犬は、腹膜炎を患うため、迅速な外科的介入が必要となる。尿腹症の猫の死亡率は 27.3% で、実験的に尿腹症を誘発し無治療の犬の死亡率は 78% で、欠損部形成後 2 日から 4 日で死亡したため、迅速な診断と治療の必要性がある。著者らの知る限り、自然発生的な尿腹症の犬の生存率を評価する研究はない。そこで本研究の目的は、初診時の血清クレアチニン濃度が予後因子になるという仮説を立て、尿腹症の犬の生存率と予後因子を明らかにすることとした。
材料と方法
2006 年から 2015 年までの2 つの獣医教育病院における医療記録を遡及的に調査し、ESCr > 2、画像診断での造影剤の漏出、または手術で尿路断裂が確認された尿腹症の犬を用いた。記録が不完全な犬は除外した。症状、診断、破裂の場所と原因、生化学検査結果、造影画像と術中所見、術前の尿抜去実施の有無、術中または術後の合併症、入院期間、生存率について比較検討した。
統計解析
フィッシャー検定を用いて、退院時生存群と死亡群間で破裂部位(腎臓、尿管、膀胱、または尿道)、破裂の原因(外傷性、医原性、閉塞性、または不明)、および術中または術後の合併症の有無について解析した。マンホイットニー検定で、生存群と死亡群間の(犬の年齢、血清クレアチニン濃度、血清BUN濃度)の差を評価した。P < 0.05で有意であるとした。
結果
性別:19 /43 (44%) は去勢雄、10 /43 (23%) は雄、14 /43 (33%) は避妊雌であった。
診断:26/29 (90%)で ESCr が2以上で、8/14 (57%) で ESKr が1.4以上、造影は 23/43 (53%) の犬で実施され、20/23(87%)で尿路破裂が診断された。
破裂部位:膀胱(n = 24 [56%])、尿道(11 [26%])、不明(4 [9%])、腎臓(2 [5%])、尿管(1 [2%])、膀胱と腎臓の両方(1 [2%])であった。原因は、外傷(n = 20 [47%])、閉塞(9 [21%])、医原性(7 [16%])、または不明(7 [16%])であった。
外科的治療
37/43(86%)が手術を受け、そのうち 21/37(57%)は術前に造影検査を受けていた。これらの犬のうち 34/37(92%)で破裂部位が特定され、外科的に治療された。3/37 (8%)の犬では、術中に破裂部位が特定されなかった。 1/3 では、尿道付近に漏出が見られ、裂傷部位は特定できなかったが尿道カテーテルの留置により治癒できた。部位を特定できなかった2/3は安楽死と死亡した。破裂部位を特定できなかった 3頭は、全て術前造影検査を実施していなかった。しかし、術前造影検査は、術中に尿路欠陥を特定する可能性と有意に関連していなかった (P = 0.07)。
記録が利用可能な36例において、術中合併症は、13/36 (36%) 発生し、低血圧 (n = 7)、徐脈 (2)、出血 (2)、regurgitation (2)、死亡 (2) であった。
記録が利用可能な19例において、術後合併症は、10/19 (53%) で発生し、死亡 (n = 3)、regurgitation (3)、持続的な尿漏れ (2)、誤嚥性肺炎 (1)、播種性血管内凝固 (1)、敗血症性腹膜炎 (1)、尿失禁 (1)、輸血を必要とする貧血 (1) であった。
手術症例3/37 (5%) は敗血症性尿腹症になったが、2頭は治療に成功し、1頭は敗血症は治せたが、陰嚢尿道造設術を飼い主が選択せず安楽死となった。
内科治療:6/43 (14%) は手術を実施せずに治療された。5/6 は尿道留置カテーテル、1/6 は閉塞性腫瘍による膀胱破裂に対して尿道ステントが使用された。破裂部位は膀胱 (n = 1)、尿道 (1)、不明 (3) であった。退院まで生存した4症例は尿道カテーテルが 3 日間 (n = 2)、4 日間 (1)、および 5 日間 (1) 留置されていた。4 日間留置されていた犬は、カテーテル除去の 3 日後に尿腹症が再発し、その後8 日間再留置され生存した。
生存率:34/43 (79%) が退院まで生存した。生存群 (6.0 ± 4.0 歳) と死亡群 (8.7 ± 4.5 歳) の間に有意差はなく、膀胱破裂と尿道破裂の間にも有意差 (P = 1.00) はなく、 腎臓と尿管の破裂に関しては例数が少なく解析ができなかった。破裂の原因(P = 0.61)、血清クレアチニン (P ≥ 0.19) または BUN (P ≥ 0.17) の濃度にも有意差はなかった。外科的治療29/37 (78%) と内科的治療5/6(83%) 間の生存率の差は有意ではなかった (P = 1.00)。術中または術後に合併症を起こした犬は、死亡率が有意に高かった。術前の腹膜カテーテル症例 7 頭はすべて生存したのに対し、カテーテルが挿入されなかった症例は 22/30(73%) が生存したが、この差は有意ではなかった (P = 0.31)。外科的治療を受けた犬の死亡率は、腹膜カテーテルを使用した病院では 6% (1/16)、他の病院では 33% (7/21) であったが、この差は有意ではなかった (P = 0.10)。
1施設では、術前に腹膜ドレナージを行い、その死亡率は 6% で、他施設では 33% であったが、この差は有意ではなかった。これは、おそらく例数が少ないためであると考えられる。これらの結果から、尿腹症の犬に腹膜カテーテルを留置して術前に管理することは賢明であると思われる。